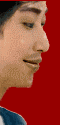
「小説」のスタンス
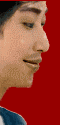 |
あとがき―― 「小説」のスタンス |
この小論は、私がこれまで書いてきた「女装小説」を、シェアテキストとしてオンラインにアップするにあたり、一般の読者の方に、「女装」という行為をなるべく偏見なく見ていただく必要を感じて書いたものです。
しかしながら、実名でこのテキストを書いたスタンスと、「前橋梨乃」名で小説を書くときのスタンスは、自ずとちがいます。
たとえば、この小論では、TV、TS、ホモセクシャルのちがいを厳密に分けるところから論じていますが、小説の方では、逆に、そこをあいまいにした表現をしていることが多いと思います。
それは、小説は大多数の人の共同幻想に依拠した表現であり、また一方で、その共同幻想が内包する矛盾をモチーフにして成立するものだと思うからです。TVなのか、TSなのか、ホモなのか、区別がつかないような状態で起こることが面白いわけです。それ以上の解釈は、読者にゆだねるべきでしょう。
本来、私が書きたいのは「面白いお話」であり、分析や解説や、ましてやメッセージではありません。
さらに言うなら、私の小説は、「現実の存在としてのTV」を書いているのでもありません。
主人公たちは、あくまで、お話の中の登場人物なのです。現実に女装する男が、私の小説の主人公たちのように「きれい」なわけはありません(たいていは、どう贔屓目に見てもやっぱりどこか「気持ち悪い」存在です。中には、100人にひとりくらい、本当に「きれい」な人がいることは事実ですが)。しかし、要するにそれは、ふつうのエンターテインメント小説でも、主人公はたいてい美男美女であるというのと同じことですし、女性の中にも、美人もいれば不美人もいるというのと変わるわけではありません。
エンターテインメントの持つ力というのは、いっとき日常を忘れ、常識を忘れ、その世界に入り込んで楽しむうちに、私たちをがんじがらめにしている日常や常識が相対化されてくることなのだと思います。だからこそ、いわば荒唐無稽な話をそれらしく読ませてしまう力技こそが命だと思っています。要するに私は、「多様な性」のひとつの可能性として、かなり無理な話を「こんなことがあったら面白いでしょ」というスタンスで、女装小説を書いているわけです。けっして、それ以上のものではありません。
ともかく、小説は、作品として(現実からも、私自身からも)独立したものです。
そういう意味では、このテキストはまったくの「蛇足」です。ここまで読まれた方には、とりあえず、「女装」という行為は、そんなに特異なことでも、またひどく異常なことでもないのだということを頭のはしにとどめる程度にして、それとはべつに、エンターテインメントとして小説を楽しんでいただけたらと思っています。