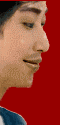
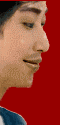 |
1.女装の「位置」 |
「女装」という行為については、精神病理学や心理学、あるいは文化人類学などのフィールドでは、「衣裳倒錯」または「異性装嗜好」というカテゴリーで扱われます。英語ではトランスベスティズム
transvestism 。vest を
trans する、という語義です。(最近ではクロス・ドレッシング
cross dressing という言葉も頻繁に使われます。)
また、こうした嗜好を持つ人々をトランスベスタイト
transvestite と言います。トランスベスティズム、トランスベスタイトともに、「男性の女装」「女性の男装」をあわせた概念です。TV(テレビのことではありません)と省略されることも多いようです。
(以下、本文でも、transvestism、transvestite
の両義でTVと略します。)
歴史的に見れば、TVという現象、TVという存在は、さまざまな時代のさまざまな地域の記録に残っています。
たとえば、ローマ皇帝のネロは、さかんに女装したといいますし、ロシアのロマノフ王朝時代に、一生を女装して暮らしたという貴族もいます。日本でも、ヤマトタケルのクマソ退治の神話にはじまり、歴史上、女装の記録は数多くあります。
また、原始宗教には、女装した男の呪者が信仰の中心になっていることも多く、インドでは今でも、そうした「女の格好をして女として暮らす男の呪者たち」が、ひとつの社会階層をつくっています。さらに、洋の東西を問わず、「まつり」に際して頻繁に女装が行われることもよく知られています。江戸時代の「おかげ参り」や「ええじゃないか」といった(時代閉塞の打破という意味をも持つ)集団ヒステリー状況でも、女装した男性(男装した女性も)が多く見られたといいます。
そうした意味では、TVは、民俗学で言う「ケ」(日常)に対する「ハレ」の表象のひとつとしてとらえることもできます。
心理学や精神病理学では、「嗜好」あるいは「趣味」としての女装は、一般に「性的倒錯」「性的病理」の一種として扱われますが、以上のような文化人類学的な背景とけっして無縁ではありません。
いずれにしても、TVは、なにも今の時代だけに見られる(病理)現象ではなく、人類社会はじまって以来、あらゆる民族のあらゆる文化に通じて見られる現象だと言ってよさそうです。
ただ、それに対して、その文化、その社会全体が、寛容であったか非寛容であったかのちがいがあるだけです。
一般に、女装している男性を見て、人々はなんと言うでしょう?
「おかま」「ニューハーフ」「ゲイ」「ホモ」「性転換」‥‥と、そんなところでしょうか。
私自身は(やたら「言葉狩り」をするような趣味はありませんので)どう呼んでもかまわないと考えているのですが、どうも、それらの概念が、著しく混同して使われている傾向があるようには思います。
TVという現象を正確に捉えるため、まず、それらをここで整理しておきましょう。「おかま」「ニューハーフ」「ゲイ」などは、俗語なのであと回しにして、
「ホモ」と「性転換(症)」と「TV」
のカテゴリーのちがいについて、次にまとめてみます。