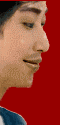
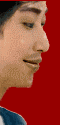 |
2.女装の「分類」 |
TVは、前述したように「衣装倒錯」。(男で言うなら)「女の格好がしてみたい」という人のことです。「女のように化粧したい」「きれいな服が着たい」、もう少し拡大すれば、「(時には)女として扱われたい」という願望があるわけです。
これを理解するには、ジェンダー gender という概念が必要不可欠です。ジェンダーというのは、おおよそ「性役割」という意味に使われる言葉で、肉体上の性=セックス
sex に対して、社会的に規定された性を表します。男女の性別から来る社会的な仕事・役割の区別もそうですが、「男らしさ」や「女らしさ」といった(その文化がもつ)「らしさの規範」をも包含しています。TVはなにより、このジェンダーを越境したいと思う人たちです。(そのため、最近ではTG=transgenderという言葉もよく用いられます。TVよりもう少し広い概念として使われることが多いようですが。)
「これは男の服装、これが女の服装」「これが男らしさ、これが女らしさ」という社会通念による縛りを打ち破ってみたい。いわばタブーを犯したい。(本人がそこまで自覚しているかどうかは別にして)そうした願望が根底にあることだけはたしかなようです。そういう意味では、TVは、肉体的なというより、観念的な願望です。
そうしたTVに対して、性転換症(精神病理学などでは「症」として扱いますが、これも「性転換指向」とでも言った方がいいように思います)は、TSと言います(※注1)。トランスセクシャル
transsexual の略です。ジェンダーではなく、セックス(肉体的性)そのものを変えてしまいたいと思う人たちのことです。じつは本人たちの認識としては、「変えてしまいたい」というより「自分は肉体的にまちがった性に生まれてきたのだ」と思っていることのほうが多いようです。「自分は本来女なのに、男の体をもっている。このまちがった肉体を(手術などで)正したい」というのがその願望です。
この点、TVが「女のようになってみたい」と思うのと大きくちがいます。TVは、自分が男だという認識があるからこそ「女のように」なのです。TSの場合は、「女に(=本来の自分に)」なりたいわけです。また、TVが、たいてい「きれいになりたい」というナルシスティックな傾向を持つのに対して、TSは必ずしも「きれいに」でなくともよいようです。「あたりまえの女になりたい」という願いがその根本だからです。自分のアイデンティティそのものが不安定なこの人たちが、じつはいちばん深刻な問題を抱えています。
いずれにしても、TV、TSは、自分の現在の性にどこか「居心地の悪さ」を感じているわけですが、これに対してホモセクシャル
homosexual は、必ずしもそうではありません。むしろ、現在の自分の性に肯定的な場合の方が多いようです。ホモは、言うまでもなく同性愛。その基本的な願望は、「性愛の対象として同性に惹かれる」ということです。ですから、なにも、自分の性を変える必要はないわけです。
「男でありながら男を愛する」「女でありながら女を愛する」という性愛の「関係」にまつわる願望であり、TV、TSが、「自分自身の性」にこだわっているのとは大きく異なります。(その点、女装した人間を見ると「ホモだ」というのは、大きなまちがいです。大多数のホモは、女装などしないものです。)
以上、3つのカテゴリーは「願望のあり方」から分類されるものです。ところが、やっかいなのは、行動様式としては、この3つがかなりの部分重なって現れるということです。
(図示すると、次のようになります。)
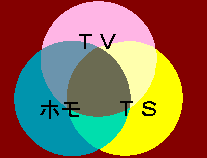
もともとの願望が3つのうちどれなのか(本人自身も)よくわからないというような中間領域が存在しますし、どれかの願望から出発した結果、行動としては、他の領域と区別のつかないところへいってしまうということもよくあるからです。
具体的に、TVの場合をとって説明すると――
日常生活は、(性生活をも含め)男としての暮らしをちゃんとやっているけれど、「趣味」「リクリエーション」として女装するという「週末女装派」という人たちがいます。というより、(ゲイボーイなどのプロをのぞけば)TVのうち最も多いのがこの集合です。多くの場合は、日常の仕事とか人間関係とかはノーマルな人と何ら変わりなく送りながら、そこになにがしかのストレスを感じていて、そこから逃れるために、ひとときジェンダーを越境してみたいと考える人たちです。これは、たとえば趣味で模型を作るとか、スポーツをするとかいうのと同じレベルの行動ですし、また、前述した「ハレ」と「ケ」の概念で容易に説明がつくでしょう。
行動としては、鏡の前で女装して楽しむだけの「鏡派」や、自分の女装写真を撮る「写真派」、また女装して外出し、それをアバンチュールとして楽しむ「外出派」などがあります。「鏡派」や「写真派」は「女のようになってみたい」というファンタジーを追う、要するにナルシシズムです。(模型づくりをする人が、その材料やさまざまな技法にこだわるように、服のブランドや化粧のテクニックにこだわります。)また、「外出派」の場合は、そこに「他人の目」を介在させて、「女のように見られたい」「女のように扱われたい」という回路で、そのファンタジー、ナルシシズムを実現しているわけです。(スポーツをする人が技の上達とその「かっこよさ」にこだわるように、女らしく見せるための仕草などの上達にこだわります。)
ファンタジーという視点から言えば、「女装」という手段が、いわば「アリスの穴」になっていて、そのことで、現実とはちがう別の世界をかいま見るわけです。
いずれにしても、この限りにおいては、四六時中女装しているわけではありませんし、女性ホルモンや手術というような手段を使ってまで肉体を女性化しようとは思いません。(「そんなことをしたら『女装』という楽しみがなくなるじゃないか」と主張する人もいます。)また、ふつう、男を相手にセックスするところまでは考えません。
ところが、中にはその趣味が高じて、自分は女として生きる方がふさわしいのではないかと思い始める人がいます。それで(プロのゲイボーイでもないのに)、ホルモン投与から睾丸摘出手術、豊胸手術までいってしまうわけです。この場合はむしろ、本来の願望はTSであったにもかかわらず、女装から入って、途中でそのことに気づくというパターンだと考えられます。
また一方で、「女のように見られたい」「女のように扱われたい」という思いを、性愛の場面にまで拡大していく人たちがいます。この場合、当然、その相手は同性である男ということになります。行動としては、まちがいなくホモセクシャルです。しかし、ここで注意したいのは、これが、「男に抱かれたいから女装する」のではなく、「女としての気分をもっと味わいたいから相手に男を選ぶ」という発想の順番だということです。その意味では(相手を利用して)自分のファンタジーを実現するという、きわめて自己中心的な性行動ということになります。このことが、なにより「関係」を重視する純正(?)ホモセクシャルから、TVが嫌われる理由ともなっています。
いずれにしても、同じTVといっても、TS、ホモセクシャルとの中間領域においては、さまざまなバリエーションが存在するわけです。
ホモ、TSの側から見たTVとの中間領域にも少し触れておきましょう。
前述したように、ホモの場合、女装などしないのがふつうです。
ところが、中には「ホモ嫌いのホモ」という面白い人たちがいます。性愛の対象としては男しか考えられないけれど、その人がホモではいやだという、いわゆる「ノンケ好み」という指向です。その場合、相手と恋愛やセックスの関係を持とうとすると、出来る限り相手の抵抗感をなくさせなければなりません。そのために、中には、相手が少しでもホモだと感じないでもすむように、(べつに女装が好きなわけでもないのに)女装する人たちがいるのです。この場合、先述したTVの場合とは逆で、「男と寝る」ことが目的で、女装はそのための「方便」でしかありません。しかし、現実の話、「女装を方便としているホモ」なのか、「セックスを利用するTV」なのかは、(その対象となってベッドをともにでもしないかぎり)容易に判断はつきそうもありません。
TSの場合は、またすこし事情が異なります。
自分の性のアイデンティティに悶々と悩んでいるうちは、たんに「女っぽい男」「男っぽい女」に見えるだけですが(注:TVの場合、日常は、むしろそう見えないことの方が多いようです)、この人たちが、いったん「決意」すると、すべてをいっぺんに変えようとします。男性TSの場合でいえば、1日24時間女装していようとしますし、恋愛の対象としては、当然男性を選びます。しかし、ここで注意して欲しいのは、彼ら本人にとってそれは、「女装」でも「ホモセクシャル」でもないということです。自分の「本来の性に合った服装」をしているのであり、女が男を愛するちゃんとした「異性愛」なのだということになるわけです。「TVが女装を楽しんでいる」のか、「TSが自分の本来のあり方として女の服を着ている」のかも、客観的には、なかなか判断がつかないでしょう。(一般に、TVの方が派手好みで飾り立てるのに対して、TSはどこにでもいるような女性の服装をするというちがいはあるようですが。)
ここで、前章で述べた、女装する男に対して一般に言われる呼び方についても、簡単に整理しておきましょう。
「おかま」というのは、もともと「陰間<かげま>」(江戸時代の男娼)から転じた言葉でしょうから、元来は「男を相手に売春をする男」という意味です。それが一般用語として、女装する男やホモに対して使われているのでしょう。
「ゲイ」は、言うまでもなく、本来英語の「陽気な」という形容詞ですが、それが、スラングとして「女のような男」を表すようになり、女装する男やホモの男を意味するようになります。アメリカの西部開拓時代など「男らしさ」が強調された時代には、男は寡黙で苦み走っていなければならず、「陽気な男などホモしか考えられない」という価値観が、そこには存在します。そういう意味では軽蔑のために使われるスラングだったのですが、時代の価値観が変わった現在のアメリカなどでは、それを逆手にとって、ホモセクシャルやTV、TSなどが(男女を問わず)自分たちをそう総称するようになっているのです。その過程で「ゲイ」という言葉の意味は広がり、また肯定的な意味合いを持つようにもなっています。(狭義には、今でも「男性同性愛者」を表します。)
「ゲイボーイ」「ニューハーフ」は、一般には、要するに「酒席で女装してサービスするプロ」の意味で使われていると思っていいでしょう。「ゲイボーイ」は昭和30年代にアメリカから入ってきた言葉で、戦後すぐには「シスターボーイ」「ブルーボーイ」などと呼ばれていたようです。「ニューハーフ」というのは、おそらくテレビ番組で作られた造語(ジャパニングリッシュですから外国では通じません)で、それが一般に使われるようになったものです。
余談ですが、この「プロ」の存在があるということでは、面白い現象が生じます。TVやTSという傾向をもつ人の多くは(特に10代でそれを自覚してしまった人は)、多少なりとも、一度はこの道に入ってみようかと思うようです。これなら、仕事として、誰はばかることなく女装できるだろうと考えるからです。ところが、実際にそれを職業とした場合、ゲイボーイとして大成(?)するのはTVの方で、TSの場合は不幸になるパターンがほとんどのようです。一見、「24時間女装していたい、体も変えたい」と思うTSの方がうまくいきそうな気がしますが、じつはゲイボーイ、ニューハーフというのは、「女を演じる男」を売り物にしているわけで、「ふつうの当たり前の女」であることをめざすTSには、居心地の悪さはけっして変わりません。むしろ、たいていの場合、さらに大きなアイデンティティの不安(「女を演じる男を演じる女」)を抱えることになります。
以上述べてきたように、一概に「女装」といっても、その願望の所在、形態はさまざまです。
その中で、私は、TVという指向に最も自分に近い感覚を持ちますし、関心もあります。
というのは、3つの中で、客観的にはTVがいちばん「ばかばかしい」からです。
「自分が何者であるのかわからない」という性のアイデンティティの不安をかかえるTSは、本人にとっては深刻で切実な問題です。また、「同性しか愛せない」というホモセクシャルも、社会生活を送る上では、深刻な問題をかかえることになります。(そうした自己の指向と社会とのギャップに悩んだすえに、実生活の面でも自分に嘘をつかず、堂々とそんな「しんどい生き方」を選択している人に、私は畏敬の念すら感じます。)
それにくらべて、「ボク、時には女の子もやってみたいもん」というTVは、じつにお気楽で、ナルシスティックで、エゴセントリックで、欲張りで、‥‥ばかばかしい存在です。
しかし、TSがもしその望みを叶えることができて、手術で体を変え、女として生活できるようになったとしたら(それは、本人にとってはやっと得られた心の平安でしょうから、私もそうなって欲しいと願わずにはいられませんが)、その行き着く先は、何度も書いてきたように「どこにでもいる当たり前の女」です。けっきょく、最後は既存の男女観の中にからめ取られていくわけです。
また、ホモセクシャルについても、そこで重要なのが「関係」、つまり「愛の相手が同性である」ということだとすると、それにこだわっている限りは(もちろん、同性間であろうがすばらしい恋愛関係は成立する、と私は思っていますが)、逆の意味で性別という縛りにとらわれているということになります。
ところが、TVというばかばかしい存在は、それ自体として「ジェンダーというもののばかばかしさ」をカリカチュアしてしまうのです。(これは、あとで論ずることになると思いますが)しょせんは人為的なものでしかない人間の性別とそのボーダーを、あいまいに取り崩して往復する存在は、硬直化した男女観に風穴をあける意味を持つと思います。
「女のようになりたい」の中の「ように」という部分が私は重要だと思っています。要するに女装はフェイクです。しょせん偽物に過ぎません。が、では、偽物があるなら、本物はあるのかという問題がそこからあぶり出される気がします。「男らしく」「女らしく」と、「らしさ」をいうなら、その「らしさ」の実体になっている「男」とは、「女」とは、いったいなにをもっていうのか、という疑問に突き当たるのです。
なんだか、もう結論めいたことを書いてしまっている気がしますが、もうひとつ、ごく具体的に、私の問題意識の契機になっていることを書いておきたいと思います。
ここまで、じつは意識的にあいまいにしてきたのですが、TV、TS、ホモセクシャルなどということは、べつに男だけに限った問題ではありません。女性にも当然あります。ところが、女性のTSはたしかにいますし、女性のホモセクシャル(いわゆるレスビアンです)もまちがいなくいるのに、女性のTVというのは、現在の日本では見あたりません。いえ、じつはたくさんいるのですが、問題にはならないのです。
女性の場合もTSやホモセクシャルは「性倒錯」の範疇に入りますが、TVに関しては、ファッションとかモードというカテゴリーの中で扱われる対象だからです。
要するに、女性の場合は、スカートでもパンツでもどちらをはいてもかまわないわけですし、ショートヘアや男っぽい服装は、マニッシュルックとして許容されます。もし、男物の背広をそのまま着ていたとしても、それがモードとしておかしくなければ、ファッションセンスがいいということになるのです。
ところが男の場合、一般には、スカートをはくことはできませんし、化粧をすることも許されません。サラリーマンなどは、仕事の場では背広にネクタイというワンパターンの服装を、事実上強要されるわけです。
男と女を比べれば、ジェンダーの許容範囲、自由度は、男の方が格段に狭いことは明らかです。
と、こう書くと、「だって、男がスカートはいたら気持ち悪いでしょ」という反論が返ってくると思います。でも、そう感じること自体が、ジェンダーの規範に左右されている結果なのだと思います。逆に、女がズボンをはくことが「気持ち悪い」(どころか「犯罪」)とされた社会すら(そんなに昔でなく、20世紀にも)あったのですから。
また一方では、フェミニズムの側からの反論も予想されます。「男の方が自由度が狭いと言うけれど、それはおかしい。世の中はいまだ男が権力を握っている男社会じゃないの」という。
私も、まさにそのとおりだと思います。社会システム上、いまだ女性が差別されていることはまちがいありません。たとえば就職差別ひとつとっても、憲法が保証する「両性の平等」などまったく空論化していると言っていいでしょう。
でも、だからこそ、私はジェンダーの問題は重要だと思っているのです。けっきょくのところ、服装をはじめとして、男の方が「らしさ」を強要されるのは、それが、男の権威づけや権力の象徴としていまだ機能しているからだという気がします。
要するに、背広にネクタイというのは、いわば聖職者の法衣であり、軍隊の軍服です。想像力も創造力も乏しいくせに、その無能力を同じ濃紺の背広という「権威」で隠した現代の司祭たちが、今日も、中央省庁や国会や財界団体の会議室で、パワーポリティクスのゲームを繰り返しています。そんな彼らを頂点とするマッチョ主義のピラミッドこそが、女性差別の根元なのではないでしょうか。
この際、男も、ジェンダーの縛りから解放されて、そんなくだらない権威のヒエラルヒーを、ずぶずぶになし崩してしまった方が、女性のためにもなると思います。
もちろん、だからと言って、男はみんな女装すべきだなどということを言うつもりはありません。ただ、そういう趣味を平気で許容することが、そんな硬直した男女観と、それに基づく社会システムを打破する突破口になるとは思うのです。