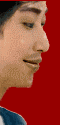
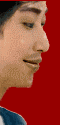 |
5.女装の「動機」 |
では、なぜ「女装したい」などと考える男がいるのか、そこのところを、もう少し突っ込んで考えてみたいと思います。
TSの場合は、ここまでに述べてきたことでほとんど解決はついていると思います。
先述した4つの性の判別法のもう一段上に、「自己認識」という5番目の項目を加えればいいのですから。それぞれの判別法の間に食い違いが起こるように、5番目の判別法との間にも食い違いが起こる。要するに、それだけのことです。食い違っている以上、(あいまいさに満ちた)性の判別に際して自分自身どの基準をとるかは、いわば任意なわけですから、自己認識を基準として、他をそれに合わせようとするわけです。
ところがTVの場合、自己認識としては明確に男だと思っています。にもかかわらず、ジェンダーを「越境してみたい」という欲望がむくむくとわき上がってくるわけです。前章でいった性のエネルギーのあらぬ方向への暴走にはちがいないのですが、その動機は、「無根拠であるにもかかわらず、けっこうきついパッチとして働くジェンダー」に対する性のエネルギーからの反発にあるのだと思います。
歴史を振り返ってみても、ジェンダーというのは、けっして普遍的なものではありません。「男らしさ」「女らしさ」の規範は、その地域、その時代の文化の様相によって、いかようにも変化しています(それがまた、無根拠であるということの証左でもあるのですが)。したがって、TVという現象が現れる具体的な道筋も、地域によって、時代によって微妙にちがってきます。ここでは、おおよそ現代の日本ということに限定して話を進めたいと思います。
「女性の性の商品化」について先に少し触れました。ところで、この「性の商品化」については、「商品化されるだけ、女はいいよな」という言い方もできると思います。
性の物語の対象として女性が商品化されるということは、女性はそのままでも「商品」たりうるということです。少なくとも、若くてある程度きれいなら、それだけで立派な「商品価値」があります。(「市場のレベル」によっては、「若い」とか「きれい」とかいうことすら「商品」としての必要条件になりません。)
ところが男の場合、(俳優やタレントなど「鑑賞」の対象となる職種をのぞけば)それだけでは商品とはなり得ません。学歴だとかなんらかの能力だとかがないことには「商品価値」を持ったものにはなれないわけです。
そんな言い方をすると、先鋭的なフェミニストからはひどく怒られるにちがいありませんが、生まれたままで商品たりうる女性の方が楽しそうに見えてもしかたないと思います。
また、「わざわざ商品になりたいのか?」という反論も当然あるでしょうが、それにしても、現実の問題として、現代資本主義というシステムの中では(「労働市場」などという言葉に端的に表されるように)、人間全般が少なからず「商品」として扱われているわけです。最終的には「自分という存在をどれだけ高く換金できるか」が、多くの場合、その人の「価値」として見られていることは、誰しも否めないことでしょう。
もちろん、女性にとって、外見だけで人間としての価値が決まってしまうようなことは心外にはちがいないでしょう。しかし、「男の価値は中身だ」というのも、けっしてラクなことではないわけです。特別の才能でもない限りは、そこには、女性以上の努力が科されるわけですから。
そんなしんどさの中で、ふと脇を見ると、「きれい」なことを自ら楽しみながら、それを「商品価値」として利用している人たちがいる。それがなんだかうらやましくて、時にはそっちの世界に行ってみたいと思ったとしても、そんなに不思議なことではないでしょう。
その「努力」や「しんどさ」に関しては、現代では明らかに男の方が(相対的に)大変なのだと思います。
歴史をたどれば、ジェンダー、つまり「らしさ」の抑圧は、つい最近まで女性の側に強く働いていました。
わかりやすく言えば、「女は嫁に行くもの」と決められていたわけです。親や社会は、その路線に沿って女の子を育てます。「男からウケがいいように」「嫁いだ家で気に入られるように」という判断基準のもと、(つまり受け身の)「女らしさ」が強制されてきました。そこでは、自らの選択肢はきわめて狭い範囲でしか許されなかったわけです。
それが、戦後の価値観の転換と、女性解放の機運が進む中で、だんだんと「嫁に行くことばかりが女の幸せではない」ということが常識になってきました。女の子も主体的、能動的に自らの道を選択することが尊重され、そのための選択肢もたくさん用意されるようになったわけです。かつて女性を縛っていた「女だから」という言葉が、今はむしろ「女だから、自由に生きればいい」という文脈で使われることが多くなっているように思います。
それに対して現在では、男の方が、選択肢が以前より狭くなっています。戦後の受験体制の中で、「いい大学に入って、いい会社に就職する」ことが、いわば絶対的価値とされ、たいていの場合、その路線に沿って男の子は育てられます。さらに悪いことには、家庭内電化や経済成長のおかげで家事労働や内職から解放された母親が、てぐすねひいてその管理に乗り出すわけです。
その結果どうなるかというと、一方で「男の子なら、もっとしっかりしなさい」などと言われながら日常をがっちり管理されるという(つまり、昔ながらの能動性を期待されながら受動的にしか成長できないという)、矛盾した環境で育てられてしまうわけです。
一般に言われる「男らしさ」には、いろいろな意味合いが含まれるでしょうが、その核になっているのが、先述したように「能動性」であることはまちがいないでしょう。「しっかりした」とか「頼りになる」というのが、「男らしさ」の本質として語られることは多いものです。ところで、この「しっかりした」とか「頼りになる」というのは、要するに社会システムの中で立派に機能しているということです。極言すれば、「男らしさ」は「社会的成功」と直結しているわけです。そのぶん、受験体制がつくり出すヒエラルヒーに従属しやすくなります。
もちろん現代では、男性、女性にかかわらず、建前としては、その能動性や自主性が重視されます。また、反面、受験体制をはじめとして、会社でも地域社会でも、(特に、日本では)「管理社会」的な側面が強いのもたしかで、そこに男女差があるわけではありません。家庭における「母親の管理」というのも、べつに男の子だけに向けられているわけではありません。そういう意味では、能動性の訓練がじゅうぶんに積まれていないにもかかわらず能動性を求められるという点では、男女にそんなに差はないでしょう。
しかし、いまだ「男らしさ」の概念が「社会的成功」と結びついているぶん、男の方が、ジェンダーの縛りがきつくなっているということなのです。
もっと簡単に言ってしまえば、(前々章にも書きましたが)マニッシュなことは、女性の魅力のひとつとして許容されても、ウーマニッシュな男というのは、多かれ少なかれ「社会的落伍者」と見なされるということです。いいとか悪いとかは別にして、それが現実です。
そんなジェンダーの縛りからいっとき逃げ出したい、あるいは(自覚的ではないにしても)それに反抗したいという気持ちが起こったとしても、これもまた、そんなに奇異なことではないように思います。
もうひとつ重要なことがあります。それは「ほめ言葉」の問題です。
人間が生きていく上で、その大きなモチベーションになるのは、他人からの評価です。人からほめられたり認められたり感謝されたりということがなければ、生きていく意欲などわいてこないものです。
ところが、女にくらべて男の場合は、成長の過程で、その評価の(特にその資質に対する評価の)言葉が大転換する時期があります。
赤ん坊から幼児期、小児期にかけて、子供に対して最も多く使われるほめ言葉は「かわいい」でしょう。そして、「まあ、かわいい子ね」というのは、いわば子供としての全存在を肯定される言葉です。たいていの人は(人によって差はあるにせよ)、そういう言葉を何度も言われて育ちます。自然と、そう言われることが、自分の存在理由の証明のように思えてくるはずです。
ところが男の子の場合は、「かわいい」というほめ言葉が、ある時期(たいていは第二次性徴の過程で)、ぱたりと使われなくなります。これはおそらく、子供にとっては価値観の組み替えを要求されることのはずです。
女の子の場合は、言うまでもなく、そのほめ言葉が長くつづきます。若い女性に対して「かわいい」と言えば「きれいだ」とか「美しい」というのとほとんど同義なわけです。(もちろん女性の場合でも、本当にかわいくない場合<‥‥すみません>、そう言われることは少なくなるのでしょうが、それにしても近所のおばさんとか親戚とかからは「まあ、かわいくなって」などとお世辞を言われたりはするのでしょう。また、女性もある程度の年齢になれば、「かわいい」とは言いにくくなってきますが、それは、男よりはずっと後、少なくとも成長過程ではありません。)
では、「かわいい」とはそもそもどういうことなのか、広辞苑によれば「かわい・い:(カワユイの転。「可愛い」は当て字)(1)いたわしい。ふびんだ。かわいそうだ。(2)愛すべきである。深い愛情を感じる。(3)小さくて美しい。」とあります。
つまり、男は、ある時期から「いたわしくなく、不憫でもなく、かわいそうでもない」存在にならなければならないというわけです。これは、前章までに書いてきた「受動ではなく能動」ということとほとんど同じことではあるわけですが、それが、最初からそうだったわけではなく、成長の途中で突然やってくるところに男の悲しさがあります。それまで培ってきた価値観が一度崩壊し、組み替えるという作業を経て、男は男になるわけです。女の子が経験しないこの価値観の大転換は、男の子にとってけっこうキツいことだと思います。
もちろん、ほとんどの男は口には出さないけれど、そんな「かわいかった自分」に対する郷愁のようなものを持っているにちがいないという気がします。
その郷愁が強ければ、時には、もう一度「かわいい」と言ってもらいたいという気になったとしても、なんの不思議もないのだと思います。
と、ここまで読んできて気がついた方もいらっしゃるでしょうが、TVというのは、よく言われる「モラトリアム現象」のひとつの現れ方でもあるわけです。
けっきょくのところ、ジェンダーというのが社会がつくった規範とするなら、「男らしい」とか「女らしい」ということは、社会で一人前と認められること、つまり「大人らしい」ということと同じことです。
子供の頃は、肉体的にも、また意識の問題としてもさほど差のない男女の性別が大人になるにしたがって両極に分かれていく。肉体的な変化はさておき、意識の面では、ボーボワールが女性について言ったのと同様に、男も「男に生まれるのではなく、男になる(される)のだ」と言えます。つまり、それが大人になるということです。
「女装したい」というのは、それに対する抵抗という側面が少なからずあると思います。世の中が(勝手に)決めた男だとか女だとかいう規範の中に入りたくない。つまり、「大人にはなりたくない」という気持ちが、そこには大きくはたらいているのでしょう。
そうしたモラトリアム的心情を是とするか否とするかは意見の分かれるところでしょうが、いずれにしても、ひとつの方向を選ぶということには必ず、それ以外の要素を捨てているという側面が付随します。「強さ」を選ぶ(選ばされる)時、そこでは必ず、自分の中にある「弱さ」を捨てている(捨てさせられている)わけです。
本来人間の中に可能性としてあるさまざまな要素のうち、「男らしさ」を選ぶということは、自分の中の「女らしきもの」を捨てるということに他なりません。いえ、捨てるというより、意識の裏側に押しやっているということでしょう。いわば、「そんなものは、自分にはないことにする」ということです。そこには、言ってみれば「もうひとりの自分」が置き忘れられることになります。時に、そんな自分を取り戻してみたいと思うのは、「全き人間」として、かなり自然なことのような気もするのですが、いかがでしょうか。