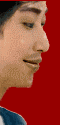
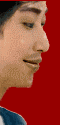 |
4.女装の「原理」 |
男性のTV、つまり女装する男は、ノーマルな人からは、ふつう「異常な奴」と見られるのだと思います。たしかに数の点から言えばマイノリティでしょうし、スタンダードでないという意味では、異「常」にちがいありません。
しかし、人間としての精神構造上、異常、つまり病的かというと、私はそうではないと思います。(その言い切りも、厳密には正確でない気がしますが、そのへんは、これから順次述べていきます。)
なぜ異常ではないかと言えば、ある意味で、それがきわめて「人間的な」行為だと思うからです。「少なくとも動物にはTVなどということはない」という意味において。
では、人間にとって「異常」とか「倒錯」とかいうことは、どういうことなのか、ここで(「女装」ということから少し離れて)考えてみたいと思います。
前項でも書いたように、女装に限らず、性的に「異常」「倒錯」というのは(サド・マゾから、スカトロ、カニバリズムに至るまで)、人間にしか見られない行動でしょう。
と、こう言うと、「でも、アザラシなんかは、一夫多妻のハレムをつくって、オスがメスを力ずくで支配してるじゃないか」とか、「カマキリに至っては、交尾のあと、メスがオスを食べるんだぜ」などという反論が返ってくるかもしれません。でも、それは、彼らの本能に沿ってやっていることです。
「本能」という言葉は、「本能のままに生きている」とかいう使い方をされるために、不当に過小評価されることの多い言葉だと思います。「本能」を正確に言えば、動物が生きていくための天与のシステムです。もう少し厳密に規定すれば「動物が環境に適応しながら個の保存と種の保存をしていくために、あらかじめ遺伝子の中に組み込まれている制御システム」だといえばいいでしょうか。防御本能とか食性とかは、個の保存のためのシステムですし、生殖本能は、言うまでもなく種の保存のためのシステムです。環境との(つまり現実との)整合性のきわめて高い良質なシステムだと思います。
アザラシも、カマキリも、けっしてその種固有のシステムから逸脱してはいません。「このカマキリはオスを食べたけれど、あのカマキリは優しいから食べなかった」などということはあり得ないわけです。メスがオスを食べるのは、カマキリにとって「異常」でも「倒錯」でもなく、本能というシステムに沿った正常な生殖行為です。
ところが、人間ときた日には、逸脱のしっぱなしです。(そういう意味で、人間の「ふしだら」な性行動を「本能のままに」とか「獣のような」と形容するのは、獣に対して失礼この上ない言い方でしょう。)
では、なぜ、人間だけに、そんな性的逸脱=「異常」で「倒錯」した性行動が起こるのか。その構造は、たとえば、こんなメタファで説明がつくように思います。
動物にとって、運動器官や消化器官などの肉体はハードウェアでしょう。そして、それを制御するソフトウェアが脳内にあることになります。脳幹だとか間脳だとか大脳新皮質だとかのややこしい説明はこの際省いて、「本能」というものを考えると、あらかじめ与えられているという意味で、それは、ROMに書かれたシステムソフトということになります。通常はリードオンリーで、書き換え不能です。人間以外の動物は、おおよそ、このROMだけで生きているわけです。だから、動物は、いわば専用機です。
それに対して、人間は、そのROMに書かれたシステムソフトの部分(つまり本能)がきわめて小さく、その上のRAMにOSやアプリケーションソフトが読み込まれてはじめて働く汎用コンピュータだといえるでしょう。経験とか教育とかがインストールされないことには、意味のある機能はしないわけです。また、つねに新たなソフトのインストールが可能です。バージョンアップもできますし、アプリケーションソフトをたくさんのせれば、マルチパーパス、マルチタスクなどという器用なまねもできます。そして、それらのアプリを支えるOSが、いわば個々の民族の言語や伝統、つまり文化でしょう。(そう言えば、「WindowsとMacでは同じデータも読み込めないんだよね」みたいなこと、今、世界中で起こっています。)
人間だけが他の動物とちがって、地球上いたる所の環境に適応して広がることができたのは、おそらくは、この「汎用性」のおかげでしょう。
ところが、どんなソフトでものるということは、ビジネスソフトではない(とりあえずの生存とはなんの関係もない)ゲームソフトやエッチソフトもそこで動くということです。けっきょく、さまざまな逸脱というのは、簡単に言えばそういうことなのでしょう。
(このコンピュータのメタファを使った説明を、調子のよいこじつけと感じる方も多いと思いますが――事実、こじつけにはちがいないのですが――、あながち根拠のないこじつけではないと思っています。人間が道具を作ってきた歴史は、自分自身や他の動物の肉体の機能の模倣・拡張からはじまると、よく言われます。その最新の成果がコンピュータであるとするなら、コンピュータは、メタファどころか、人間をモデルとしたレプリカントそのものだからです。)
構造はそういうことだとして、でもまだ、そんな構造がどうしてできたのか、つまり、本能というROMの部分がどうして小さくなったのか、その説明がついていません。
いえ、じつを言うと、私の実感としては、構造の説明としても、前項の説明ではじゅうぶんでないという気がしています。どうも、人間の場合、本能が小さくなったというより、そのROMが(あるいはそこに書かれたプログラムが)不良品で、「バグだらけ」だということなのではないかという気がするのです。
というのは、エロス(あるいは、フロイト流に言えばリビドー)というような人間のエネルギーの強さを見ると、どう考えても、本能そのものが(量的に)小さくなったとは思えないからです。
本能というプログラムのコーディングだけはとりあえずされているのに、それがじゅうぶんに構造化されていない。だから、プログラムの断片が個々に暴走してしまう。人間の本能は、そんなバグでいっぱいなのではないでしょうか。
重いプログラムのわりにはバグだらけで、そのままでは使いものにならない(つまり、個の保存も種の保存もままならない)から、しかたなく、文化というソフトウェアで「パッチあて」をした。前項で書いた人間の「汎用性」というのも(けっしてそんなに威張れる話ではなく)、単にその結果得られた副産物にすぎないのではないか。と、そんな感じがするのです。
本能がバグだらけだという理由は、たとえば、アドルフ・ポルトマンの「生理的早産説」などでも説明がつくと思います。
ポルトマンによれば、人間は、「生理的に早産が習慣化してしまったサル」なのだといいます。おそらくは直立二足歩行のせいで(つまり、子宮が「縦位置」についているせいで)、本来なら胎児が胎内で発育するのに必要な時間、母親のお腹の中にとどまっていることができなくなった。いわば未熟児のまま、早産されることがふつうになってしまった動物が人間だということです。
世の中に生存する多くの動物の中で、生まれ落ちたままの状態では一日たりとも生存できないのは、おそらく人間だけでしょう(サルも多少、そのきらいはありますが)。なにしろ人間の赤ん坊ときたら、ウマやキリンのように歩くことはもちろん、自ら母親の乳まで這ってたどり着くこともできないのですから。目さえほとんど見えない状態です。
目がないわけではない。手や足もそろっている。そんなふうに機能の要素はとりあえずあるのに、それがちゃんと使えるほど発育しない状態で生まれてきてしまうわけです。
生存のためのシステムである本能にも、これと同じことが言えるのではないでしょうか。とりあえず、プログラムらしきものは書いてあるけれど、それをじゅうぶんにデバッグできないうちに「納期」が来てしまう。その結果、バグだらけのシステムプログラムで、人間はこの世に「出荷」されるというわけです。
こんな不完全な動物が、これまで絶滅せずに生存してきたことが、不思議です。もしかすると、サルから人間になる過程で、ほとんどの群はすぐに絶滅したのかもしれません。しかし、たまたま、あるひとつの(あるいは少数の)群が、群というネットワーク機能を最大限に使うことで、かろうじて、そのぼろぼろの本能にパッチをあてることに成功した。それが、文化の誕生の瞬間であり、言語の誕生の瞬間なのだと思います。
しかし、パッチは、しょせんパッチに過ぎません。どこまで行ってもつぎはぎなのです。本来の生存のためのシステムがバグだらけなのだから、どこかに必ずほころびが現れます。
あらゆる方向に向いて暴走しようとする本能に、ちょっとやそっとのパッチ(倫理や社会通念、法や制度など)をあてるくらいでは足りそうもありません。でも、やたらパッチをあてまくればいいかといえば、そうでもないようです。時には、そのパッチをあてたことが、システムプログラムの新たな思わぬ方向への暴走を招いたりもするからです。さらに、まるっきり見当はずれなところにパッチをあてることも多いものです。その結果、パッチプログラム自体が暴走してしまうことさえあります。
それは、性についてもまったく同じです。というより、ネットワーク機能が働きにくいスタンドアローンな行為としての性行動の面で、よりその傾向が強く現れるように思います。
と、こういう書き方をすると、社会の中の一部の人が「暴走する」のだと受け取る方もいるでしょうが、ここで言っているのは、そういうことではありません。人間の性行動というのは、いわばすべてが「暴走」の要素を含んでいるものであり、「逸脱」しているということです。
本来、哺乳類などの生殖のシステムを見ていると、たいていの場合は「さかり」というシーズンがあり、子供の成育にとって最も適した自然環境の時期に出産が重なるように出来ています。そのことひとつとっても、きわめて環境との整合性のある最適化されたシステムだといえます。いずれにしても、動物の性行動というのは、あくまで「生殖のための行為」です。(一部のサルには、コミニュケーションや群の維持のために生殖行為を利用するものがいるようですが‥‥。)
これに対して人間の場合は、「さかり」はありませんし、むしろ、ほとんどの性行為は(意識の上でも、また実態としても)「子供をつくるため」ではありません。これを、本来の種の保存のためのシステムからの「暴走」「逸脱」と呼ばずして、他にどう呼べばよいのでしょう。
では、「子供をつくるため」でないとするなら、人間は、なんのためにセックスをしているでしょう。多くは快楽のためであり、と同時に愛情の確認やコミニュケーションや、時には征服欲や、あるいは、打算や保身や出世や詐欺や‥‥その他もろもろのためでありうるわけです。
つまり、バグだらけのROMを抱えている結果として、人間の性行動は、本来の動物のあり方から言えば、すべてが「異常」であり「倒錯」だと言っていいものになっています。
これが、フロイトの言う「人間の性はそもそも多形倒錯である」ということなのでしょう。
さらに大事なことは、このバグだらけのROMは、単に暴走するというだけでなく、そのままでは本来のタスクすら満足には果たせないということです。
動物の場合、たとえば、子供の頃に捕らえたひとつがいを、動物園の檻の中に入れておいても、成獣となり「さかり」の時期が来れば、たいていは自然に生殖行為に及ぶものです。(ゴリラなど一部の類人猿はそうでもないらしいのですが‥‥。)これは、つまり、本能の中にその「やり方」までがプログラムされているということです。
ところが人間の場合、何らの「学習」もなしにセックスすることは、おそらく困難でしょう。もちろん、ここで言う「学習」とは、学校での「性教育」など(だけ)を指しているのではありません。「セックス」という言葉(つまり観念)に興味を持ち、友達どうしで「情報の交換」をしたり、辞書などを調べた経験は誰しもあると思います。また、その類のノウハウ本はいくらでもあります。そういう「学習」の経験をたどらないことには、具体的な「セックスの方法」を、人間は「思いつかない」のではないでしょうか。
(かつて、「青い珊瑚礁」というブルック・シールズ主演の映画がありました。難破船に乗り合わせた少年と少女が無人島にたどり着き、二人だけで暮らす間に子供ができてしまうというようなストーリーでしたが、あんなことが本当に可能かどうか、たぶんに疑わしいと思います。)
人間の生殖本能は、勝手に暴走するばかりか、ほかっておけば、その「正しいやり方」にはたどりつけません。もっと有り体に言えば「成熟した異性の性器」には到達できないのです。
その結果、そのエネルギーは、容易に他のものにとりついてしまいます。それは、未成熟の子供でもいいわけですし、同性でもいいわけです。さらに言えば、鞭とローソクというシチュエーションでも、死体でも、人間以外の動物でも、なんなら、下着や赤いハイヒールでも、そして、蝶のコレクションやパソコン、模型づくりや、過度のスポーツで自分をいじめることでも、権力を握るために執念を燃やすことでも、なんでもいいわけです。
当然、そのままでは、性のエネルギーが生殖行為につながらないわけですから、「種の保存」などおぼつかないでしょう。そこで文化は、その暴走に必至になってパッチあてをしようとします。
ポルノグラフィは、有史以前からあるのだといいます。遺跡の壁に、男女が睦み合っている絵が発見される例は、数多くあります。
要するにポルノは、人間の性のエネルギーを、「正しく」異性の性器へと導くために、どうしても必要なものなのだと思います。(とはいうものの、ここにも人間の「バグだらけ」の本能のシステムが反映して、性のエネルギーを「まちがった」方向へ導こうとするポルノもたくさんあります。たとえば‥‥私の小説だとか。)
ともかく、たいていのポルノは、「密壺」だとか「濡れた入り江」だとか、その他じつにさまざまな形容の限りをつくし、性器をすばらしいもの、まるで人生最終最大の到達点であるかのように描き出します。つまり、あらゆる方向に向かおうとする人間の性のエネルギーを、なんとか異性の性器へと向かわせるために、ポルノは、人類文化が採用した「涙ぐましいパッチプログラム」なのだと言えるでしょう。
そこで、もうひとつ、「猥褻」ということも考えてみたいと思います。
「ヘアヌード、是か非か」という論争などばかばかしいかぎりですが、「性器を見せない」というタブーには、なにより、性器を「神聖」なものにしておこうという意図がはたらいているのだと思います。
本来、性器など、要するに人間の器官のひとつに過ぎません。
それを「隠す」ことによって、「特別なもの」とする必要が、どうしてもあるのでしょう。「神聖」で「特別」だから見てみたい。そこにたどり着きたい。なにかそれを「宝物」のように扱うことで、暴走する人間の性エネルギーを、そちらに向かわせようとしているわけです。
そういう意味では、刑法の「猥褻物陳列罪」の条項は(「表現の自由」という点からは問題があるにしても)、人類文化の「正しい」戦略だといえるでしょう。
前項では、わかりやすい例としてポルノと言ったのですが、じつは、「愛と性」にまつわるほとんどの物語は、人間を異性とのセックスに至らしめるためのパッチプログラムとしての機能を果たしているのだと言っていいでしょう。もちろん、愛を描いたすべての小説や演劇や映画がそのためだけにあるなどとは言いません。しかし、それに感動し、共感する(あるいは劣情をそそられる)ことで、異性に対する愛情(や欲望)が補完されることは事実でしょう。
逆に言えば、そうした「物語というパッチプログラム」なしには、人間は、性のエネルギーを生殖行動につなげることはできないのだと思います。小説や映画ではないとしても、人間は、必ず何らかの物語にあてはめることで、二人の関係を築くものです。
「愛によって結ばれた二人」は、「愛」という物語(つまり、パッチプログラム)の中に自分たちの関係を位置づけてセックスに至るわけです。もちろん、この「愛」を「運命」に変えて、「運命によって結ばれた二人」という物語も成立します。
あるいは「信仰によって結ばれた二人」でもいいわけですし、「夢」でも「理想」でもいい。「趣味」でもいいし、場合によっては「お金」という物語でもいい。さらに言えば「本能によって結ばれた二人」という関係もあり得ます。(もちろんこの場合の「本能」は、「本能という物語」であり、先刻から言い続けている「バグだらけのROM」でも、動物本来の「種の保存のためのシステム」でもありません。)
いずれにしても人は、それらのうちのどれかの(あるいはその二人独自の)物語を採用して、そのプログラムに沿って恋に落ち、セックスに至るという道筋をたどるものです。(人間以外の動物の場合は、そんな面倒で不健全なことはせず、天与のシステムに沿って、ただ生殖するだけです。)
そして、そうだとするなら、「男と女」という両極の存在もまた、人為的な「物語」に過ぎないのだと思います。「世の中には、男と女という二種類の人間しかいない。正反対の存在だからお互いに惹かれ合うのだ」という大物語が前提としてあり、その大物語のもとで(前述したような)それぞれの小物語がつくられた方が、まちがいなく「種の保存」には都合がいいわけです。「男と女」という物語も、けっきょくは、文化によってつくられたパッチプログラムに他ならないのではないでしょうか。
と、そんな言い方をすると、「馬鹿なことを言ってはいけない。男と女では体のつくりがちがうじゃないか。動物としてのオスとメスの区別は明確にあるだろう」という反論が返ってきそうです。
たしかに、男の体と女の体では構造がちがいます。しかし、その肉体にしても、男と女という単純な二分法が成り立つほど簡単なことではないらしいのです。「性は、連続性を持つものである」というのが、ここ半世紀ばかりの生物学・生理学の常識です。
動物の雌雄を判別するには、だいたい4つの方法が用いられます。歴史の古いものから並べると――まず1つ目は、外性器の形態のちがい。要するにペニスかヴァギナかのちがいです。2つ目は、内性器のちがい。哺乳類で言えば、精巣なのか卵巣と子宮なのかのちがいです。3つ目は、性ホルモンの構成のちがい。男性ホルモンか女性ホルモンかのちがいです。そして4つ目が、遺伝子、つまり性染色体のちがい。XYなのかXXなのかというちがいです。
このうち、1番目の外性器と2番目の内性器は、仮性半陰陽(外性器と内性器が合致しない形態をしている)、真性半陰陽(外性器・内性器が両性の特徴を持っている)という大きなくくりに含まれる多種多様な中間体の例が、想像以上に多くあります。(※注1a)
3つ目のホルモンにしても、オスの体内にも女性ホルモンはありますし、メスも男性ホルモンを多く持っています。そして、その構成比の個体差はさまざまです。だいいち、「コレステロールから、まず女性ホルモンである黄体ホルモンがつくられ、それがテストステロンなどの男性ホルモンにつくりかえられ、さらにその男性ホルモンを芳香化してエストラジオールなどの女性ホルモンとなる」という、体内での性ホルモンの組成過程ひとつを見ても、それが相反する別のものではなく、連続性のあるひとつのものだということが言えると思います。
現在、最も確かな判別法としてオリンピックのセックスチェックなどにも用いられているのが、4番目の性染色体によるものです。しかし、じつはこれにも、さまざまな性染色体異常(つまり中間体)の症例が報告されています。それに、そんなセックスチェックが必要だということ自体が、4つの基準で判別した男女の性が、実際にはそれぞれ食い違ってしまう、ボーダーのあいまいなものであることの証明に他なりません。
つまり、生物学的には、オスとメスという「性」は、さまざまな相で連続性を持つ「傾向」なのであって、けっして二項対立するものではありません。(※注2)
にもかかわらず、(そのセックスチェックに典型的に現れているように)人間は、是が非でも男女を分けようとします。そこには、必死になって「男と女という物語」を守ろうとする、人類文化の恣意性を感じずにはいられません。(※注3)
生物学的に見てもそんなあいまいな基盤の上に立っている「性別」を唯一の根拠として、「男らしさ」「女らしさ」、つまりジェンダーは規定されているのです。逆に言えば、その根拠が脆弱だからこそ「らしさ」が強調されるのかも知れませんし、また、本来なら、その脆弱さを補完するはずの本能がいいかげんだからこそ、「らしさ」のパッチあてをしなければならないのでしょう。
いずれにしても、いわゆる「男らしさ」「女らしさ」として語られるもののほとんどは、後天的な「物語」なのであって、天与のものであるとは思えません。
その「男らしさ、女らしさ」という物語の最も中心にあって、かつ、多くの人に信じ込まれているのが、セックスの場での「能動と受動」ということです。
男はアグレッシブに女を犯し、女の方はあくまで受け身でそれを受け入れるのだという構図が、性の物語の中ではスタンダードであり、それが、男と女の属性だとも語られます。そして、男の「強さ」「剛毅さ」「活発さ」、女の「弱さ」「やさしさ」「おとなしさ」というのも、おおよそ、その構図から導き出されてくるものでしょう。
そう言われる根拠は、要するに構造上、(少々下品な言い方になりますが)男は「突っ込む」側であり、女は「突っ込まれる」側だから、ということでしょう。
しかし、これなど、完全に(文化としての)レトリックの問題だと思います。「女はくわえ込む側で、男はくわえ込まれる側だ」と言ってしまえば、簡単に逆転してしまうのですから。
けっきょくのところ、「男と女の物語」の最大のものである「能動性と受動性の神話」こそ、バグだらけの性本能に対する、最大のパッチプログラムだという気がします。
しかし、セックスの場面で、男と女に構造上からくるちがいがないかと言えば、そうではありません。唯一の絶対的ちがいは、男はつねに「不能」を前提としているということです。
純粋に構造上の問題だけで言えば、女の方は、成熟さえしていればいつでも性行為が可能です。それに比べ、男の側は、勃起しなければできないわけです。要するに、男がその気にならないことには生殖行為は成立しません。つまり、男は、常態においては「不能の性」だということです。男の側に「能動性」を求める事情はここにあります。
ましてや、その男の性のエネルギーが(前述したように)まったく別の方向に暴走してしまって、女性の性器に向かわないのなら、種の保存など満足にできるわけがありません。したがって、人間を「正常な」性行為に導くためのパッチは、もっぱら男に対してあてられます。世の中のポルノグラフィの99パーセントまでが、男に向けられてつくられているのは、そのせいです。
そしてそこに、よく言われる「女性の性の商品化」のひとつの理由もあります。つまり、ポルノグラフィー(あるいは、それに類する商行為)が男に対して向けられるなら、そこで対象(つまり商品)となるのは、当然、女だからです。
(じつは、「女性の性の商品化」には、他にも大きな理由があります。それは、性行為にまつわるもうひとつ大きな男女のちがいとして、そのあとに女性の妊娠<直立二足歩行での危険な妊娠!>ということがあり、その上、そこで生まれてくる子供が、前述のように、大人の保護なしには生きていけない存在であるということです。人間という動物が、首尾よく「種の保存」を成し遂げるためには、生殖行為だけでなく、この過程すべてが保証されなければなりません。つまり、妊娠中の女性と生まれたばかりの赤ん坊を保護するシステムがどうしても必要なのです。そこでつくられたパッチプログラムが「家族制度」ということでしょう。女には「母性」というパッチが、男には「家族を保護し養う義務」というパッチがあてられます。そして、男がその「義務」を免れるという契約の上に、賠償金をあらかじめ払って行われる性行為が「売春」でしょう。そのあたりについては、「結婚制度」なども含め、もっと詳しい分析が必要だと思いますが、本題からだいぶそれてきているので、ここではやめておきます。)
以上、長々と述べてきましたが、要するに言えることはふたつあると思います。
第一に、人間には満足に機能する本能がないため、そのかわりに文化による観念操作が必要不可欠だ。そのひとつとして、種の保存をしていくためには、ジェンダーという規範がどうしても必要になるということ。
第二に、ところが、そのジェンダーの中身、つまり「らしさ」として語られることに何らかの根拠があるかといえば、じつはほとんど(そうした便宜的な意味以外には)ないのだということ。
――です。
そこに、TVなどという奇妙なことが起こる原因があります。
TVは、ある意味でまちがいなく「異常」ですが、しかし、そんなことを言えば、人間のすべての性行動は「異常」ということになります。私が章頭で、TVは「人間として」異常ではないといったのは、そういう意味です。